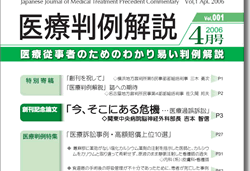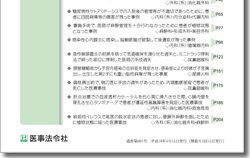|
本誌は、単に過去の医療事故を広報的な趣向で掲載していくのではなく、1つ1つの事例を法律家・医療従事者、双方の目を通じて解析し、裁判所が出した判断を正しく又は批判的に認識していくことに重点を置いた形で事例を紹介していきます。
そのため、各事例の冒頭サマリーでは、法律用語を極力省き、医療関係者にも理解頂ける言葉遣いや解釈を付記しています。これによって、裁判ではどのように理論が展開され、どのような手順を踏まえて判断し、結果として何がポイントとなって判断されたかが容易にご理解頂けるようになっております。
また、文中「専門医のコメント」において、臨床医による客観的な所見を見ることも大変重要なポイントと考えております。
『裁判において争点となった手技は、専門医から見て、どの程度難易度があるものか?』
『率直な見解として、今回の事故は、通常の医療従事者にとって防ぐのは困難な状況か?』
『今回の事故は、他の病院でも頻繁に発生する可能性はあるか?』
『自分が当事者だったら? 我が病院で行った場合、どう対応するか?』
など、できるだけ実際に臨床医学に携わる専門科の医師に所見を頂き、客観的な解釈も載せています。
こうした主旨をご理解いただき、本誌を病院の安全管理、若手医師の育成において活用して頂ければ幸いです。
|